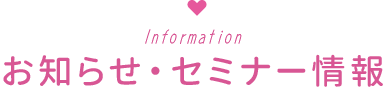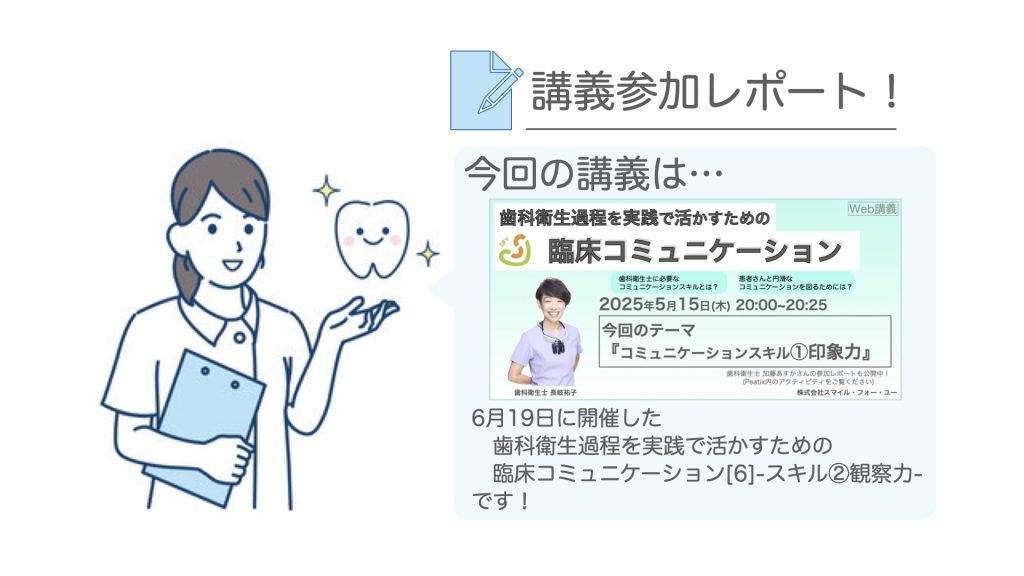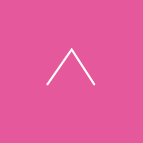6/19(木)のSFYオンラインスクールは『臨床コミュニケーション⑥観察力』についてでした!受講して学んだこと、感じたことをまとめます!
講義内容は
・5つの“みる”-違いを理解する-
・ SFYが求める観察力
・観察力の高め方
歯科衛生過程に必要な「情報」を集めるには、患者さんの様子や違和感への観察が必要になる。
普段の患者さんの状態(様子)を覚えておき、異変があったときにわかるように、常に観察することを歯科衛生士は癖づけておくこと。
観察力を高めるには、訓練が必要で
1.判断基準をもつ(決めておく)こと
2.静的観察と動的観察
3.患者導入
が重要とのことでした。
また、”みる”にも5つあり、
1.見る:目でものをみる
2.視る:意識して注意深くみる
3.診る:医者が患者のからだをみる
4.看る:世話をしながらみる(看護・介護)
5.観る:じっくり味わってみる
自分は今どの目線で「みている」のか、意味を理解したうえで臨床で行動していきたいと思いました。
判断基準については、正しい状態への知識を学んでおき、それを基準に正常なのか、異常状態なのかを判断していくこと。
静的観察は、髪の毛や着ている服、ネイル、メイクなどから感じられること。
臨床で例えば、髪の毛を染めている人が根本から色が抜けていたた場合、最近忙しいのかな、見た目に頓着がない人なのか、だらしがない人なのかなど、予測をして観察をしたりします。
髪の毛のパサつきがあれば、乾燥からなのか、栄養が取れていない髪質なのか生活状況を想像したりもします。
動的観察は、表情、体の動き、仕草、癖などから感じられること。
臨床で例えば、患者さんと会話をしているときに、目がキョロキョロとしていたり、眉間にしわが寄っていたりすると、今の内容理解できていないな、何かのワードで不安にさせたかな、まだ緊張されているかな、など観察から読み取り、わからなかったところはなかったかを聞いたり、わざとゆっくり話をしたり次の行動の選択や、声掛けをすることができます。
患者さんを待合室からユニットに導入するときが、一番観察ができる瞬間だったりします。
名前を呼んだときの表情、歩き方、今日の服装、会話をしているときの雰囲気、会話のテンポなど、口腔外の情報収集をして、口腔内を観察していくことは歯科衛生過程には大切な要素になると改めて思いました。
明日の臨床から「観察力」を意識し、患者さんの健康増進に貢献していきたいと思います!
次回の『臨床コミュニケーション』は、7/3(木)20:00~20:25 ⑦メディカルインタビューについてです!
▼25min Online School 入会はこちらから!▼
https://sfy-online-school.com/items/63a3c99d2cdd546ef96e9054
オンラインスクールの講義は、毎週(木)20:00~20:25です📖
一緒に25分で濃い学びをし、臨床に活かしていきましょう!
歯科衛生士 加藤あすか
https://www.instagram.com/asuka11101/
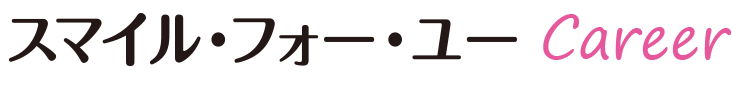
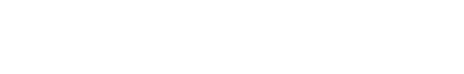

 は給付金の取扱いが出来る職業紹介事業者です
は給付金の取扱いが出来る職業紹介事業者です